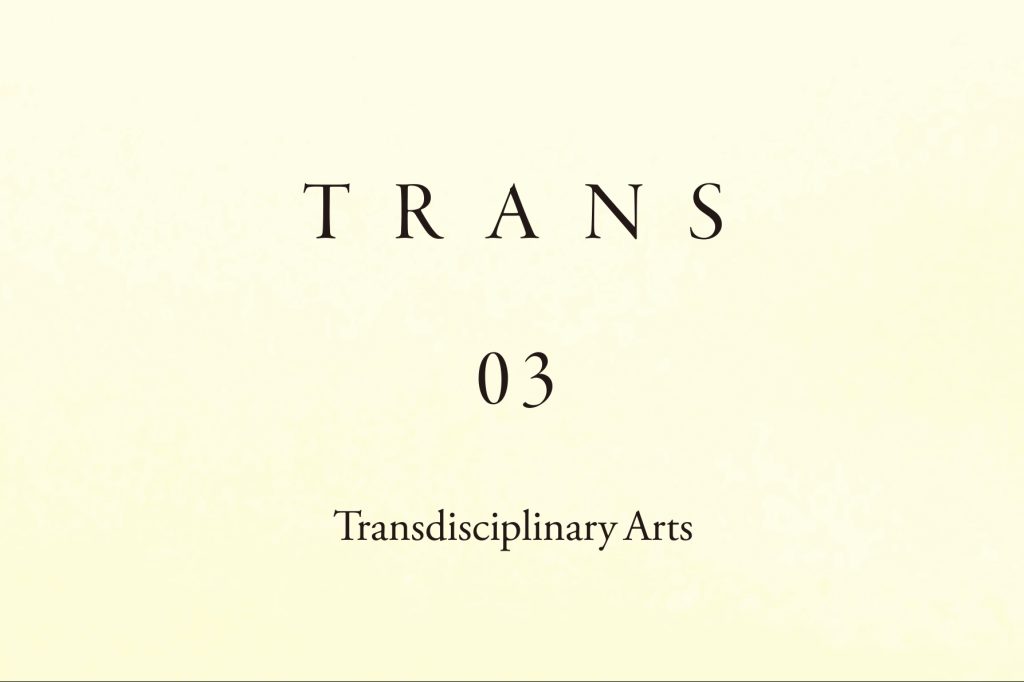複合芸術研究科の広報誌『TRANS 03』を発行しました。
複合芸術科広報誌『TRANS 01』、『TRANS 02』に続き、『TRANS 03』を発行しました。
本記事末尾にてPDFデータも公開しております。ぜひご覧ください。
Editor’s Note
「美術」はそもそも複合的だった──。本研究科の客員教授、北澤憲昭先生の主著『眼の神殿』(ちくま学芸文庫、2020年)を改めて読み返すと、そのことを重々思い知らされます。それは、1873(明治6)年のウィーン万国博覧会に参加する際、その出品分類に記されたSchöne Kunstというドイツ語を翻訳した造語でしたが、この官製訳語に「西洋ニテ音楽、画学、像ヲ作ル術、詩学等ヲ美術ト云フ」という註がつけられたことから、美術は絵画や彫刻ばかりか、音楽や詩を含んだ、今日でいう諸芸術の意味をもっていた事実を、北澤先生は解明しました。それは、その語の成り立ちからして、さまざまなアートを内蔵していたのです。
もうひとつ、北澤先生が同書において指摘した重要な点は、日本語にはそのアート(art)にたいするネイチャー(nature)に相当する語もないという厳然たる事実でした。唐木順三の「おのづからがみづからであることの構造」に見られるように、わたしたちの祖先は自然を客体として突き放すことも対峙することもなく、だからこそ明治の日本は西洋近代の原理である主観 – 客観という構えを学ばなければならなかったのでした。写実という技法をとおして事物を客体化してとらえた一方、そのようにしながら主観を育んだ現場こそ、近代洋画の歴史にほかならない──。それが北澤史観の要諦です。
以上の2点を踏まえるならば、複合芸術を提唱する本研究科が、じつのところ日本近代美術史の中心に立脚していることがわかるはずです。複合芸術は、美術の本来的な複合性に由来している点に加えて、さまざまな社会実践をとおして客体化と主観の相互作用を繰り返しているからです。日本近代美術の中心が秋田という辺境の地にあるという逆説の、なんと痛快なことでしょう!
ただ、この逆説がまことに生きるのは、中心と周縁の、現在と過去の、そして主体と他者のあいだを線で力強く引くことができるときのみです。諏訪論考における「棄民」をめぐる粘り強いフィールドワークは、岩井論考および高山論考における「移住民」についての芸術実践とはっきり結びつけられています。美術の内外を分ける線そのものを相対化したのが、山梨論考でした。
本号に潜在するさまざまな線を探し求めて、どうぞご笑覧ください。
『TRANS』編集長 福住 廉